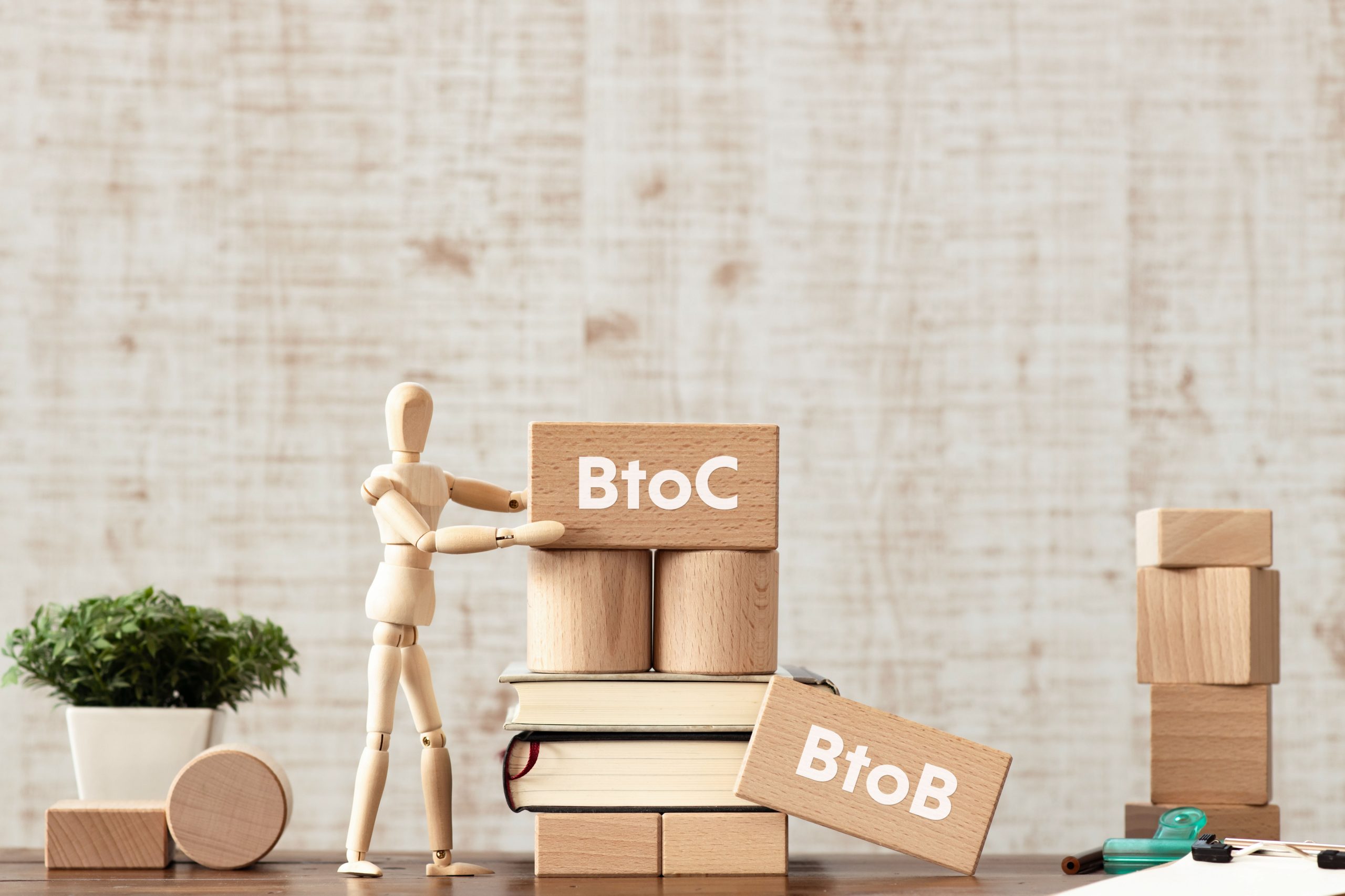物流知識
現場でどう活かせるの? 物流ロボットについてわかりやすい解説
2025.04.30

EC需要がますます増加・多様化する一方で、深刻な人材不足も進んでいる物流業界。
近年、この喫緊の課題に対するソリューションとして「物流ロボット」へのニーズが高まっています。
今回は物流ロボットの主な種類とそれぞれの特徴、導入にあたってのポイントとされる事柄を解説します。
物流の現場を変えるテクノロジーの基本を見ていきましょう 。
物流ロボットとは?
物流の倉庫作業のうち、たとえば「運ぶ」「仕分ける」「積み上げる」といった工程を人の代わりに自動で行うのが物流ロボットです。
その市場規模は、人材不足の解消や倉庫業務の効率化を求める各社が物流システムの見直しを図ろうとする中で広がりを見せ、今後さらなる拡大が予測されています。
機能に特化した産業用ロボットですから、もちろん映画やアニメで描かれるようなヒト型ではありません。
行う作業の内容や範囲によって種類も形態も異なり、現場ごとの自動化ニーズに合わせてさまざまに活用されます。
ここでは大きく「搬送系」「ハンドリング系」「自動倉庫」の3つのカテゴリーに分け、それぞれの役割や特徴をご紹介します。
「搬送系ロボット」とその特徴

搬送系の物流ロボットは、人間で言えば「足で歩く」役割を受け持ち、人に代わって倉庫内の荷物を運びます。
走行の方式により、さらに「AGV(無人搬送ロボット)」と「AMR(自律走行ロボット)」の2タイプに大別されます。
両者の主な特徴は次の通りです。
AGV(Automatic Guided Vehicle )
・床面に敷かれたガイドライン(磁気テープなど)をたどる誘導走行。
あらかじめ決められた経路しか走行することができない。
・無人で荷物の搬送・運搬を行う。
1990年代頃から、工場の生産ラインなどで使われてきた。
・決まった経路だけを往復する搬送に特化している分、導入〜運用が比較的容易とされる。
・ガイドラインを敷設する際、現場設計やレイアウトの見直しが必要になる場合がある。
また、搬送経路の変更にはその都度ガイドラインを敷き直す手間やコストがかかる。
AMR(Autonomous Mobile Robot)
・センサーで検知した障害物や周りにいる人物を回避しながら、最適な経路を自ら判断して自律走行。
・人と協働し、作業を補い合う前提で設計されている。
(例:人の手で荷物や商品を載せ、タブレット端末等で搬送先を指示、AMRが目的のエリアまで運ぶ)
・AGVより歴史が浅く、次世代型ロボットに位置付けられる。
・ガイドラインが不要なので、既存の現場レイアウトのまま導入しやすい。
逆に、導入後にレイアウト変更などが生じた場合も柔軟に対応できる。
・AGVよりも導入コストが高くなるケースが多い。
運用コストやメンテナンスも想定しておく必要がある。
コンベアのように単純な搬送に適しているAGVと、よりフレキシブルに作業環境への対応が可能なAMR。
それぞれに違いはありますが、倉庫内の省力化、物品をムダなく移動させることによる搬送作業の効率化といったメリットは共通して期待できるでしょう。
「ハンドリング系ロボット」とその特徴

ハンドリング系の物流ロボットが担うのは、「手で荷物を扱う」役割。物品を取り出したり、仕分けたり、積み上げたりする作業です。
人の腕を思わせる形状からアームロボットとも呼ばれる「垂直多関節ロボット」が代表的なもので、ファクトリーオートメーションの主流にもなっていますが、物流の現場では荷物のピッキングやパレタイズに活用されています。
垂直多関節ロボットの特徴としては、次のようなものが挙げられます。
垂直多関節ロボット
・関節にあたる「軸」を複数設けることで、人の腕のように繊細な動きを可能にしている。
・人の手に相当する先端部分=「エンドエフェクタ」を用途に応じて選べるため、汎用性がある。
・設置面積に対してアームの可動範囲が広く、360度回転や伸縮も可能。
スペースの少ない現場や既存のレイアウトを変えたくない場合でも導入しやすい。
・AIなどによる学習・計算機能を搭載したり、カメラやセンサーを取り付けたりすることもできる。
・誤作動や故障に備えた定期メンテナンスや、運用コストを想定しておく必要がある。
たとえば荷役台(パレット)に荷物を積み付けるパレタイズの際、形状やサイズ、重さが異なる荷箱を崩れないように整然と積んでいく作業は人の手では難易度が高く、肉体的な負担も大きいものです。
荷物を認識するAIとカメラを搭載した垂直多関節ロボットは、このような工程の高精度な自動化を可能にします。
「自動倉庫」とその特徴

自動倉庫は文字通り、現在は人が担っている作業を自動化させた倉庫のことです。
今や夢物語ではなく、ロボット同士の異なる働きをコンピューター制御で連携させ、ピッキング、搬送、入出庫といった一連の工程を自動で行わせている事例が大手配送業者やECサイトなどの倉庫には見られます。
自動倉庫の特徴を以下に整理しておきましょう。
自動倉庫
・倉庫内作業全体を自動化することで、従業員の負担が軽減され、安全性が高まる。
・24時間稼働でき、生産性が向上する。
・商品を取り間違えるなどのヒューマンエラーを大きく低減できる。
・人的な作業スペースが不要になり、倉庫内の空間を最大限に使える。
特に人が作業することの難しかった天井方向のスペースもムダなく活用できる。
・自動化の規模が大きくなる上、倉庫に応じたカスタマイズが必要で、導入コストが膨大になる。
また、システム障害が発生した場合の影響が倉庫業務全体に及んでしまう。
物流ロボット導入のポイント
ここまでに見てきたように、省力化・正確性・作業効率といった点がメリットに挙げられる物流ロボット。
導入にあたって、現場ではどのようなことが検討されているのでしょうか。
ロボットに代替させる作業の明確化
物流作業の自動化といっても、どこから始めたら良いかわからない企業も少なくないようです。
どの範囲の工程をロボットに行わせるかが定まらなければ、導入をイメージすることは難しいでしょう。
また、必要な機能を具体的にしておかなければ余計な 機能のためにムダなコストをかけてしまったり、目的にそぐわないロボットを導入してしまったりすることも起こり得ます。
自社の作業ラインを精査して課題を抽出し、それがロボットによって解決できる問題かどうかを検討しておくことが、導入計画を進めるうえで 必須と言えそうです。
現状の倉庫レイアウトを変更するかどうか
物流ロボットの種類によっては、現在の倉庫内のレイアウトを変更する必要が生じることはすでに述べた通りです。
スペースをつくるためにレイアウトを変えるとなれば、その作業が完了するまで業務をストップする事態も想定しなくてはならないでしょう。
既存のレイアウトを変えない方向で考えるなら、搬送系ロボットのAMRという選択肢がぐっと有力になります。
また、単に今あるレイアウトを変えるというのではなく、新たな物流拠点を別に設けたり倉庫を増設したりという方向にビジョンを広げ、それらの計画に合わせてロボットの導入を図るケースも見られるようです。
費用対効果の検証
どんな物流ロボットにも言えることですが、せっかく導入しても投資に見合うだけの効果が得られなければ、それはそのまま損失につながります。
多くの企業がコストを慎重に検討するのは当然で、無理のない予算規模の設定はもちろん、投資に対する効果や費用の回収期間のシミュレーションは必須でしょう。
シミュレーションは将来的な視野に立ち、この先の労働力人口の減少の影響、人件費、物量といった、業界をめぐる環境の変化を考え合わせることが重要になります。
まとめ
今回は、主な物流ロボットの種類別の役割・特徴と、導入にあたって多く検討されているポイントを解説しました。
業界全体が直面する人材不足に加え、国内にとどまらないECの拡大傾向とこれに伴う荷物量の増加への備えとして、物流ロボットへの期待はさらに高まっていくでしょう。
まだ現実的には考えていなくても、ロボット導入の将来的な可能性を含め、自社の業務を見つめ直す上でひとつの参考になれば幸いです。