物流知識
BtoB倉庫とBtoC倉庫の特徴・違いや、今後注目される物流ビジネスの新潮流について
2025.01.27
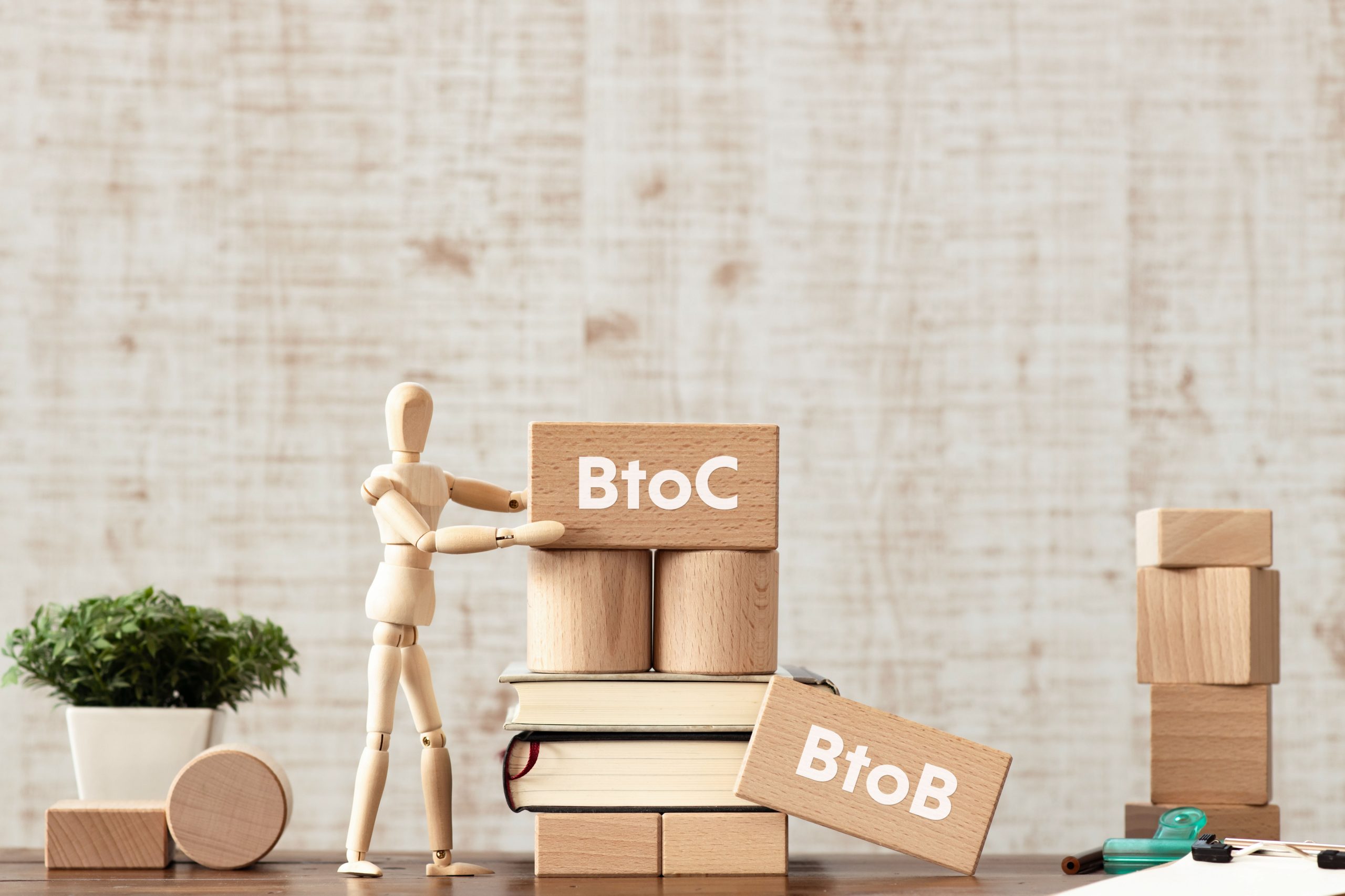
ビジネス用語として知られる「BtoB」と「BtoC」ですが、物流倉庫においてもBtoBとBtoCがあるのをご存じでしょうか。
今回は、「BtoB倉庫」と「BtoC倉庫」の特徴や違いとともに、今後の物流ビジネスの新潮流として注目される「BtoB・BtoCの両立物流管理」について解説します。
そもそも「BtoB」「BtoC」とは?
まずは、ビジネスシーンでよく使われる「BtoB」「BtoC」の意味を、あらためて確認しておきましょう。
BtoBとは「Business to Business(企業から企業へ)」の略で、企業間で取引されるビジネスのことを指します。商品やサービスを提供する側と、それを購入・利用する側が、それぞれ法人組織であればBtoBとなります。例えば、家電を製造するメーカーと、その家電を販売する小売業者との売買取引などが該当します。
これに対して、BtoCとは「Business to Consumer(企業から消費者へ)」の略で、企業と一般消費者の間で取引されるビジネスのことを指します。企業が提供する商品やサービスを購入・利用する側が消費者であればBtoCとなります。例えば、小売を事業とする企業が、一般消費者へ商品を販売するなどの取引が該当します。
これと同じく、物流倉庫においても、商品を取引する相手が企業か一般消費者かによって、「BtoB倉庫」と「BtoC倉庫」の2つに分類されます。
「BtoB倉庫」とは?その特徴は?
BtoB倉庫とは、企業に販売する商品の保管、在庫管理、入出荷業務などを行う倉庫のことです。取引する相手が大口の企業や卸売業者となるため、運用管理などの業務において以下のような特徴があります。
BtoB倉庫の主な特徴
●1納品先に対する出荷量が多く、同一商品を百単位、千単位、場合によっては万単位で出荷する場合もある。
●出荷先の多くが長期契約した取引先企業となるため、出荷予測が立てやすい。
●同一商品をケース単位でパレット保管することが多いため、高積みが可能な天井高の倉庫スペースや、フォークリフトが必要となる。
●在庫の情報は、ケースの外装に品番や商品名、数量などの明細を記載して一括管理することが多い。(ケースに添付したバーコードをスキャンし、中身の情報をデータ管理。)
●取引先ごとの納品ルールが細かく定められており、取引先から指示された物流システムを導入する場合もある。(バーコードなどの印字にも数ミリ単位の基準が設けられていることが多い。)
「BtoC倉庫」とは?その特徴は?
一方でBtoC倉庫とは、一般消費者に販売する商品の保管、在庫管理、入出荷業務などを行う倉庫のことです。取引する相手が個人の消費者となるため、運用管理などの業務において以下のような特徴があります。
BtoC倉庫の主な特徴
●一つの納品先に対する出荷量は、同一商品や他の商品を含めて1~3点程度、多くても10点程度と比較的少ない。
●出荷先が不特定多数の個人客となるため、出荷予測が立てにくく、宛先確認作業の正確性が求められる。
●多種類の商品を少量ずつ保管する「多品種小ロット」の在庫が基本となるため、倉庫内のロケーションや棚割りが複雑化しやすい。
●取り扱う伝票枚数(受注件数)が多く、伝票あたりの出荷量は少ないため、伝票ごとに商品をピッキングする手間が多くなる。
●個包装やセット商品の組み合わせ、納品書や請求書、チラシ、プレゼントの同梱など、荷主が指定する顧客サービスに応じて、細かい庫内作業が発生することもある。
「BtoB倉庫」と「BtoC倉庫」の決定的な違い

ここまで見てきたように、BtoB倉庫とBtoC倉庫の運用管理においては、それぞれに特徴や相違点がありますが、決定的な違いとなるのが、一つの商品を「どこに」「どれだけ」発送するかという点です。その違いによって、日々の業務で求められる対応や重視すべきポイントなども大きく異なってきます。
BtoB倉庫に求められる対応・重視すべきポイント
BtoB倉庫は、一回でまとまった数量の商品を、取引のある決まった企業に出荷するのが主要業務となります。そのため、大量の在庫を保管・管理・出荷するためのノウハウや環境整備とともに、特定の業界や企業の要件に特化した的確な対応が求められます。そのようなことから、一般消費者との直接的な関係性よりも、取引先企業とのパートナーシップや専門性の高い対応力が重視されるといえるでしょう。
BtoC倉庫に求められる対応・重視すべきポイント
これに対してBtoC倉庫は、多品種小ロットでの受注が多く、不特定多数の消費者に直接商品を出荷するのが主要業務です。扱う商品や出荷サービスの品質は、その商品に関わるメーカーや小売業者、配送企業など、すべての関係者に対する消費者からの信頼を左右します。商品の扱い方や梱包、伝票ひとつをとっても、不備があれば関係者へのクレームにもつながりかねないため、顧客(消費者)一人一人の満足やニーズを重視した、きめ細かい柔軟な対応力が求められるでしょう。
物流ビジネスの新潮流として注目される「両立物流管理」

BtoB・BtoCともにEC市場の規模が年々拡大
ここ最近、スマートフォンの普及やECサイト(ネット通販)の利用者が増加したことを受け、EC(電子商取引)市場の規模が年々拡大しています。経済産業省の「電子商取引に関する市場調査の結果(※)」によると、令和5年の国内におけるBtoBのEC市場規模は465.2兆円(前年420.2兆円)、BtoCのEC市場規模は24.8兆円(前年22.7兆円)となっています。とくに、BtoCにおけるEC市場の約7割を占める物販系分野の伸長が著しく(前年比9.2%増)、消費者のECサイトを通じた物品購入が確実に定着しつつあることを示しています。
BtoBとBtoCの垣根はなくなりつつある
こうしたEC市場の伸長により、ECサイトを活用したBtoCに新規参入するBtoB企業も増えており、物流ビジネスにおけるBtoBとBtoCの垣根は徐々になくなりつつあります。そうした中、将来的な物流のビジネスモデルとして注目されているのが、BtoB倉庫とBtoC倉庫の業務を一元化した両立物流管理です。BtoBとBtoCの在庫を同じ拠点で一元管理することで、さらなる販路の拡大やリードタイムの短縮、在庫切れによる機会損失の防止、拠点集約によるコストダウンなど、さまざまなメリットが得られると期待されています。
BtoBとBtoCの両立物流管理に向けて
ただ、BtoB倉庫とBtoC倉庫は、運用管理の手法やアプローチが大きく異なるため、双方の両立にはまだまだ課題が残されているのも事実です。その解決策としては、デジタル技術の活用や企業間の連携・ノウハウの共有など、さまざまな方法が考えられますが、今後どのような新技術や施策をもって双方を両立させ、物流ビジネスの新たな潮流を生み出していくかが、将来の物流業界の進展に向けたカギとなってくることは間違いないでしょう。
まとめ

本文今回は、BtoB倉庫とBtoC倉庫それぞれの特徴・違いや、その両立に向けた今後の物流ビジネスについて解説しました。
普段の業務において、自社が「BtoBかBtoCか」を意識することは少ないと思いますが、ビジネス上のターゲット像をしっかりと捉えることは、業務品質や売上の向上にも大きく役立ちます。ぜひこの機会に、BtoB・BtoCというビジネス形態への認識を深め、自社業務や今後の物流のあり方について、あらためて考えてみてはいかがでしょうか。





