安全・品質
物流における4M(Man・Machine・Method・Material)
2021.02.10
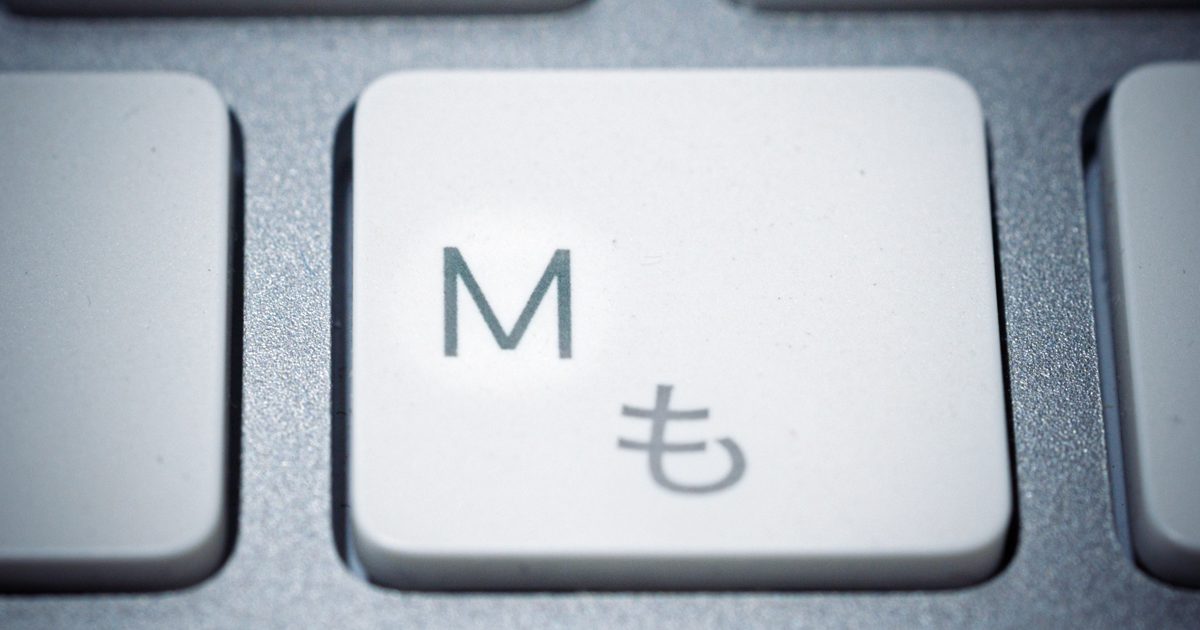
品質管理の4Mの使いみち
品質管理の4Mとは
そもそも品質管理の4Mとは、品質に影響する4つの要素、作業者(Man)・設備(Machine)・作業方法(Method)・材料(Material)のことです。もともと製造業で開発されたフレームワークです。機械を用いた大量生産を行う製造系の現場を前提として考えられたフレームワークですが、さまざまな産業で応用することが可能です。
特性要因図と組み合わせて使う
特性要因図とは魚の骨のような形で品質に影響する要素を書き出す図のことです。別名フィッシュボーンチャートとも呼ばれます。
品質の特性に対して影響を与える要素の分類として、4Mを使うことで特定の分野に関する要因に偏ってしまうのを防ぐことができます。
図を作成するときの大骨にあたる部分に4Mを使います。特性要因図の作り方については以下の記事を御覧ください。
4M変更管理の要点として使う
「4M変更管理」とは、変更したときに品質に影響する可能性のある4つの要素を管理するという考え方です。4Mに関わることを変更したときに記録をつけておき、品質に何らかの変化が起きた際にその記録と照らし合わせて原因を探ることで、品質の維持をはかります。
物流における品質管理の4Mとは
物流現場における4Mは作業者(Man)、現場環境(Machine)、作業内容(Method)、商品特性(Material)の4つです。
作業者(Man)
作業者の年齢、経験年数、夜勤か昼勤かなどの勤務時間帯、残業時間などの要素です。
現場環境(Machine)
使用しているマテハン、設備、機械、その他作業環境などの要素です。
作業内容(Method)
作業方法、マニュアル、作業に関するルール、作業の負荷などの要素です。
商品特性(Material)
外装や梱包方法、内容物の重さ、破損のしやすさなど取り扱う商品についての要素です。
製造業における4Mの違いや派生フレームワーク
製造業における4Mとは
製造業の4Mは、作業者(Man)、設備(Machine)、作業方法(Method)、材料(Material)の4つです。
作業者(Man)は経験年数、年齢、国籍など、作業者に関わる要素です。特定の属性に偏ってミスや事故が起きている場合、その裏に何か共通点がある可能性があります。
設備(Machine)は、機械の機種、何号機か、メンテナンス状態など、設備に関わる要素です。特性の設備に要因があり、問題が発生している場合があります。
作業方法(Method)は、作業の方法のことです。手順が間違っている、教育方法に不備がある、などの要因が考えられます。
材料(Material)は、投入する材料のことを指します。原材料や前工程の品質にばらつきがあるなどの要因が考えられます。
5M+1Eなど派生フレームワークもある
4Mから派生したフレームワークとして、5M+1Eや6Mといったフレームワークもあります。これらは4Mにそれぞれ別の要素を足したフレームワークとなっています。上記で紹介した4Mに入っていない要素のみご紹介します。
・管理(Management):いわゆるマネジメントのことです。作業を管理する手法や管理者などです。
・媒体(Media):作業者と機械の間に入る要素のことです。温度や湿度、騒音などの作業環境や教育や指示の方法など広く含みます。
・測定(Measurement):検査の方法や測定誤差などの要素です。
・環境(Environment):作業環境のことです。
現場によってはこれらの項目を独立させたほうがもれなくまんべんなく分析・管理可能な場合もあるので参考にしてみてください。
現場ごとに取捨選択していい
4Mというフレームワークは絶対的なものではありません。現場や扱うものごとによりあてはまりのよいものが(Mから始まる単語に限らず)あるはずです。使いづらいなと思ったら、減らしてみたり増やしてみたりすることをおすすめします。
現場ごとに構造も工程も特性も違う以上、フレームワークも取捨選択するのは自然なことです。
まとめ
物流における品質管理の4Mについて紹介しました。品質に影響を及ぼすものをリストアップする際のとっかかりとして、4つのMとして覚えておくと着手しやすくなります。取り扱う商材や取引慣行ごとにさまざまな形態になる物流現場においても、ある程度この記事で紹介した4Mで対応できるのではないでしょうか。慣れてくるとより自社の現場にあった項目も見えてくると思いますので、増やしてみたり省略してみたりするのもよいかと思います。





